STAFF紹介
助産師 田辺 けい子先生

私は、ながらくジェンダーやフェミニズムの文脈から社会科学的に無痛分娩をめぐる諸相を論じてきました。と同時に「助産とは何か」という問いを問い続けています。下の枠内に記した6項目は、この2つの問いが交差する問い“無痛分娩に助産師はどうかかわるべきか”を考える際のロジックです。2019年に記しました。ですが、日向俊輔先生、野口翔平先生という心強い同志を得た2023年のいま、新たに№7を加えたいと思います。
7.麻酔や分娩の知識を得ることによって、私たちの助産診断は深みを増し、より豊かで正確な助産技術の提供を可能にします。これを具現するのが飛ぶ無痛Caféです。
無痛分娩に求められる助産を探求することで、助産という営みの新たな地平を拓きたい、拓けると信じているのが私です。
〜(前略)では助産師は今後、どのようにあるべきなのでしょうか。6つの考え方(ロジック)を提案します。
- 自然分娩か無痛分娩かではなく、自然分娩にも無痛分娩にも、助産を求めている人がいる限り、助産師は助産を提供します。
- これまで手つかずだった「無痛分娩における助産」を探求することは、すなわち、助産そのものや助産師の職能の広がりを探求することと同義です。
- 無痛分娩における助産を探求することは、反転して、より良い自然出産の助産について考える契機にもなります。
- ながらく自然出産に深くコミットしてきた助産師だからこそ見えてくる、無痛分娩における助産の「知」を構築すべきです。痛みさえなければ「満足のいく出産」や「いいお産」になるというわけではありません。
- 医学的な周産期医療管理体制を強化・整備するだけでは、真の安心は提供できません。
- 麻酔や分娩の知識は、医師からも学ぶことはできます。しかし、助産は助産師にしか伝えられません。無痛分娩において「助産」の専門性が発揮しうるか否かは、今、無痛分娩に携わっている現場の助産師、一人ひとりの内発性にかかっています。
(出典)『無痛分娩と日本人』(2019年)から「無痛分娩に助産師はどうかかわるべきか—-“自然か無痛か”から“自然も無痛も”へ(55〜57頁)」一部抜粋
経歴
資格/役職
著書
メディア
麻酔科医 日向 俊輔先生
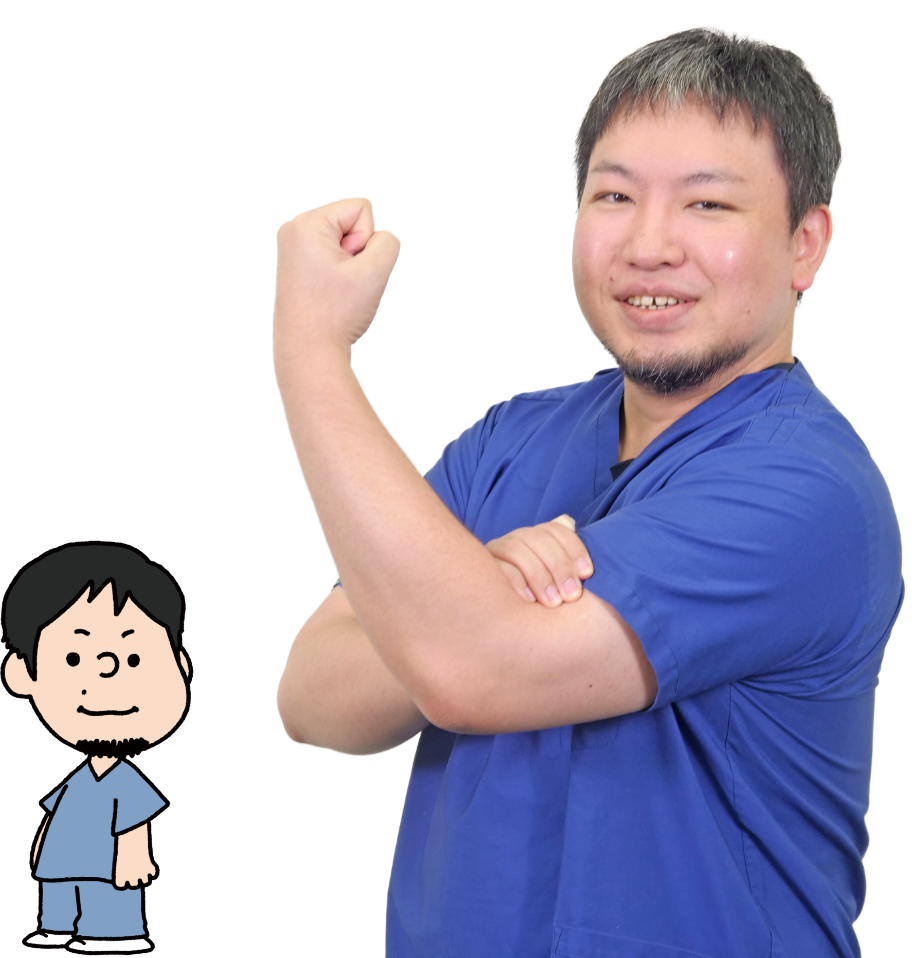
私は産科病棟常駐型の産科麻酔科医として日々無痛分娩や帝王切開術の麻酔、産科救急疾患への対応をしています。
痛みのない、かつ分娩進行を妨げない無痛分娩を行う知識や技術を鍛錬してきましたが、ある時、痛みを完全にとっているのにあまり幸せそうでない産婦さんに出会いました。
そこで気づきます。私はあくまで分娩の1要素である陣痛を無くしているに過ぎず、分娩にはその産婦の妊娠経過、家族背景、社会的背景、バースプラン、ありとあらゆる要素が有機的に結びついているものであると。良いお産には全人的で様々なアプローチが必要であり、それには助産師さんや産科医、新生児科医との協働が必須であるとも。
この飛ぶ無痛Caféでは、安心・安全・快適な無痛分娩のノウハウを助産師さんにお伝えするとともに、無痛分娩をきっかけに良いお産を一緒に考えていけるコミュニティ形成を目指しています。無痛分娩を通じて得られる喜びも悩みも共有して、みなさんのステップアップに貢献できれば幸いです。
経歴
資格/役職
賞罰
産科医 野口翔平先生

お産すること、病に伏すこと、亡くなること。
そんな人生における重大な時に、そのひとが自分らしく、良い様にいられること。
わたしが目指すのは支持し共歩する医療です。

